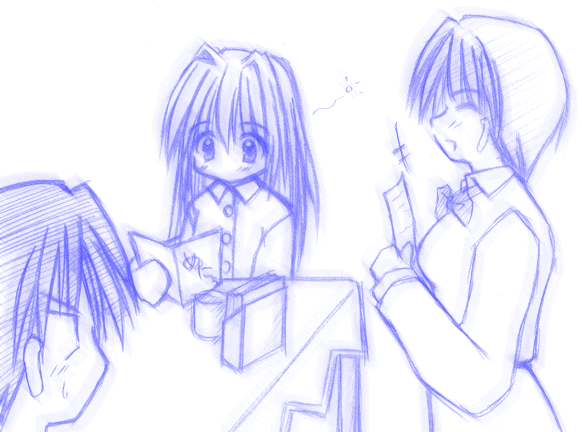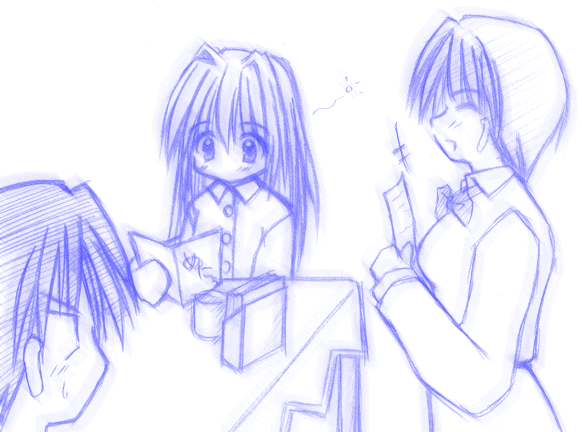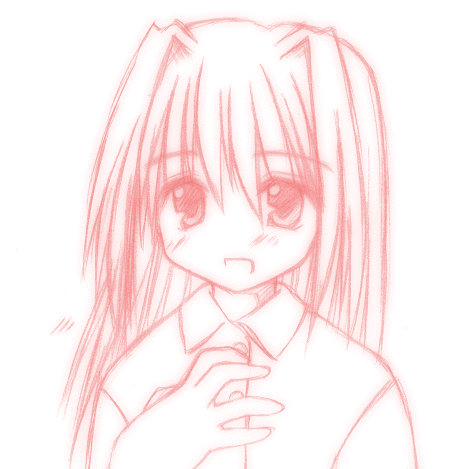「祐一〜一緒に帰ろ☆」
「あれ、部活はいいのか?」
「今日はお休みー」
「ふーん…珍しいな。そーだな…じゃ、せっかくだし商店街でも寄ってくか」
「うんっ!行くよー遊ぶよー」
今にも”にゃー”とでも鳴きそうにごろごろして喜ぶ名雪。他に適切な表現が思い浮かばないくらい、猫そのものだった。
嬉々としてカバンに荷物を詰め込んで、あっという間に帰る準備を整えてしまう。
「さ、早く行こっ」
「おう」
ぎゅ、と名雪が祐一の手を掴む。祐一のほうも慣れているのか驚きもしない。
「えへへー、ゆーいちといっしょだー…」
心底から嬉しそうに、名雪。
手を小さく繋いだまま教室を出て行く。
教室に聞こえてくる会話がだんだん小さくなり、やがて周りの音にかき消されていった。
はあ、とため息をつく者が一人。
「…あいつら、遠慮ってもんは知らないのか?」
「名雪にしてみれば、何年も暖めてた恋が実ったわけだしね…無理はないんじゃない?」
男の独り言に、律儀に返事を返す女の声。
彼女のほうに振り返る。
「…そんなもんか?」
「不満そうね。もしかして北川君、あのコ狙いだった?」
ぶんぶんっ。
男…北川はその言葉に慌てて首を横に振る。
「とんでもないっ…俺はなぁ…あのな…えーと……」
しごろもどろになって言葉を詰まらせる。
女は…香里はその北川の様子にも特に興味なさそうにそっぽを向く。
「ふーん…別に、どうでもいいけどね」
「………」
北川は、悲しそうだった。
「主よ、人の望みの喜びよ」 〜ラブラブなゆちゃん劇場2〜
「どこ行こうか?」
「祐一と一緒だったらどこでもいいよ〜」
「そんな適当な事言ってると速攻でホテルに連れ込むぞ」
「いいよ♪」
………
時間が止まった気がした。
「…………いや、ここはツッコんでくれないと困るところ…」
ボケもツッコミも万能の祐一だったが、今回は脳が対処しきれなかったようだ。
「そうなの?祐一のことだから本気だと思った」
「お前なぁ…」
はた、と言葉を止める。
本気だと思った。名雪は本気に受け止めていた。その上で「いい」と。
そうすると、そういうことは…
ほら。
「………」
妄想にふけるうちに、無意識に繋ぐ手に力がこもっていく。
(だ…ダメだ、俺としたことがまたコイツのペースに…)
名雪もあわせるようにきゅ、と握り返す。
「………」
「………」
「…祐一、えっちな事考えてる」
「ぐあっ…」
当然のようにバレていたらしい。
名雪は笑いながら、ぴた、と祐一の右腕に体を寄せる。
「あのね…私も♪」
祐一は、一瞬気を失った。
やっぱり、無難にいつもの喫茶店になった。
「いつもの」
「はーい。じゃ、いつものココナッツミルク入りすいかチョコレート半熟あんみつカレー風味デラックスね〜」
「…違います」
くすくす、と注文を取りに来たウェイトレスが笑う。いつもいつも来ているのですっかりお馴染みの顔だ。
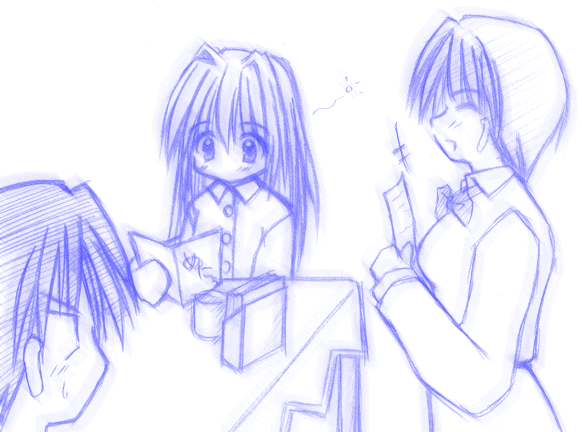 「冗談よ〜、ちょっと食べた人の反応見たかっただけなの〜」
「冗談よ〜、ちょっと食べた人の反応見たかっただけなの〜」
「ホントにあるんかいっ!」
よく見ると、メニューの右端に確かに載っていた。ただし、写真は無い。
祐一は想像し…ようとしたがそれすら敵わなかった。特に「半熟」が強敵だ。
「いつものコーヒーよね〜、エスプレッソ指定で〜」
「…そうです…」
「で、名雪ちゃんはいちごサンデーでいいのね〜?」
「うんっ」
元気よくうなずく。いつも変わらない笑顔だ。
つられるようにウェイトレスの子も笑う。
「あはは、本当にいつも仲良しね〜、お姉さん羨ましいわ〜」
言うだけ言って、注文を持ってカウンターに向かって行った。
それを確かめて、祐一が軽くため息をつく。
「はぁ…どうも、あの人は苦手だ…」
「そうなの?私は好きだよ〜」
「…そーいやどことなく似てるな…お前ら…」
マイペースというか、掴み所がないというか。
その代表格が秋子さんかも知れないが。
とにかく、自分のペースに持っていけない。
「似てるんだったら、好きなんじゃないの?」
「よく言うな、お前も…」
何の躊躇もなく言ってのける度胸が恐ろしい。
どちらかと言えば、普通はここは「じゃあ私の事も苦手なの?」という方向性ではないだろうか。
「まあ、別に嫌いだって言ってるわけじゃないさ。苦手ってのは、こう…なんか、いつもの俺のペースで話が出来ないというか」
「…意識してるからじゃないの?」
「違うっつーに。なんかさ、ふと命令されたら何でも聞いてしまいそうな」
「ゆーいちー、あたしね、前から欲しかった靴があるの。買って♪」
「…やっぱ、違うか」
「うー…」
残念そうに唸る名雪。結構本気だったらしい。
「はぁい、お待たせ〜」
その話題の当人がコーヒーを持ってきた。ナイスタイミングだ。
数分後には、もう既に実物を見なくても正確にスケッチできそうな程良く見てきた、お馴染みのいちごサンデーが届く。
「ん…幸せ〜」
言葉どおり本当に幸せそうに、スプーンをくわえながら目を潤わせて感激する名雪。とてももう何十回と食べてきたという様子には見えない。
「………」
その顔をぼーっと見つめてみる。
(何回見ても…凶悪に可愛いんだよなぁ…)
この時は本当に、その笑顔を独占できる自分が世界一幸せ者なのではないかとも思う。
そしてすぐ、そんな事を思う自分がちょっと悔しくなる。
祐一はいつもこの繰り返しだった。
「祐一?…食べたいの?」
あまりに放心状態でじっと見つめていたため、名雪からも不信がられる。
「ん…いや…」
しかしその名雪も一瞬後には閃いたようににっこりと微笑む。
「しかたないなぁ、じゃあ私が食べさせてあげるね」
「え!?いや、待て、俺は別にいらんから…」
「ほら…はい☆」
スプーンに―――もちろん、つい先程まで名雪が使っていたものそのままだ、バランスよく一口ぶん取って、祐一の目の高さあたりまで近づける。
いわずと知れた、「あーん」というやつだ。恥ずかしいことこの上ない行為上位5位に必ず入るとも言われるアレだ。
「い、いや、本当に、いいって。名雪が全部食べろよ」
「ほら、早くしないとアイスが溶けちゃうよー」
聞く耳持たない。
(嫌だ…俺はそこまで堕ちたくない…っ)
しかし、時間が経てば経つほど周囲の注目が自然に集まるのもまた事実だった。
加えて、名雪は引きそうにもない。
(…くっ…仕方ない、それならいっそ、少しでも早くこの苦痛から脱しなければ…)
覚悟を決めてスプーンに口を近づける。
なるべく自然さを装ってゆっくり口を開ける―――
からんからんっ
「ほら、お姉ちゃん、向こうの席が空い―――」
ちょうどそのタイミングで店内に入ってきた人物と、見事に目が合った。
あまつさえ、非常に良く見知った顔だった。
その一瞬で、全ての思考回路が凍りつく。
「…だからこの店は止めておいたほうがいいって言ったのに」
後から入ってきたもう一人が、ため息と共に呟く。
祐一はまだ硬直したまま動けなかった。
ついでに、最初に入ってきた女の子のほうも固まっている。
「祐一〜、溶けちゃうー」
祐一は机に突っ伏した。
「この状況に何の反応も無しか…お前は…」
「え?…あれ、香里だ。それに、栞ちゃん?」
今初めて気づいたと言わんばかりの名雪の反応。というより、本当に気づいていなかったのだろう。
「…栞、そろそろ生き返ったら?」
香里が硬直したままの妹に冷静に声をかける。
「祐一さん…短い間ですが、今までお世話になりました。…お元気で…」
ぱたん。
栞は、魂が抜けたまま体だけが脊椎反射でしゃべっているような声で言うと、そのまま踵を返して店を出て行った。
やれやれ、と再度ため息をつく香里。
「遺書には確実にあなたの名前が載るわよ…相沢くん」
ぱたん。
いつもの、どこか面倒そうな表情のまま捨て台詞を残し、去って行った。
「………」
「………」
奇妙な沈黙が場を…店内全域を包み込む。
「…何があったの?」
「あああっ!こいつはああぁぁぁぁっ!?」
その沈黙を簡単に破ったのは名雪の、極めて単純な一言だった。
祐一は頭を抱えて絶叫する。ついでに、律儀にもコケるふりをする周囲の客。
具体的に言葉に出して説明する気にはなれず―――出来るわけがない、祐一はただ、心の中で泣いた…
「たっだいま〜」
当然、あれから他の場所に寄る気にはなれず、そのまま帰ってきた。
でもやっぱり玄関をくぐる直前まで手は繋いでいる。
「おかえりなさい。あら…今日は二人一緒なんですね」
「秋子さん…俺は一人の少女から未来を奪ってしまったかも知れない…」
「あらあら、大変ね」
ごんっ。
祐一は玄関の壁に頭をぶつけた。いつもの事ながら、大変さのカケラも感じない口調。
「ゆういち、どうせ栞ちゃんに何かヘンな事したんでしょ」
「したのはお前だっ!どっちかっつーとっ!」
「私、なんにもしてないよ〜」
全く自覚がないからどうしようもない。
二人とも話している間に靴を脱いで、玄関に上がっている。
「まあまあ、もうご飯出来てますから、後でゆっくりとお話して下さい」
「はーい」
「はい…」
ばたばたと二人揃って洗面所に向かう。
結局、その話題が出される事は2度と無かった。
「いっただきまーすっ」
「いただきます」
「ビーフシチューだ〜おいしそ〜」
いつも通り食事時になると5歳くらい幼くなる名雪がはしゃぐ。
いや、というより…
「名雪、今日は随分と嬉しそうね。いい事でもあったかしら?」
「久しぶりに祐一と一緒に帰れたのー」
「そう、良かったわね」
あまり何の感慨も無さそうに同意する。ただ慣れているだけかも知れない。
祐一も、最初はあまりに何もかも正直な名雪にドキドキの連続だったものだが、もうすっかりこういう会話にも免疫がついていた。
(もう何を言われても平気さ…ふ、成長したな、俺…)
「祐一ね、いきなりホテルに連れ込むなんて言うんだよ〜」
「言うなああああああああぁぁぁっ!!」
早くもウィルスは免疫よりも進化していたらしい。
「あらあら…ダメですよ祐一さん」
「い、いえ、ほんの冗談のつもりででして…あの…」
「せっかく同じ家に住んでいるのに、もったいないじゃないですか」
「は、はい……………はい?」
きょとん、と祐一。
「あら、そういえば今夜用事があったの思い出したわ…ちょっと出かけてくるわね、1時間半ほど」
にっこり、といつもより数段明るく微笑む。
「……あ、あ、秋子さんっ…」
言わんとするところを察して、真っ赤になって動揺する祐一。
怒られるとは思っていたが、全く違う切り口だった。
一方。
「あれ?お母さん、あれ確か来られない人がたくさん出て、もっと時間かかるって言ってなかったっけ…2時間くらい」
「あらあら。そうだったわね、忘れてたわ…大変ね、9時くらいまで帰れないかも知れないわ」
9時、を強調して言う。
(あ、アホな…)
まだまだ水瀬家の恐ろしさを分かっていない祐一であった。
「ホントにどこか行っちゃうし…」
頭を抱える祐一。
「大切な用事だからね…大変なんだよ」
リビングのソファに腰掛けて適当なテレビを見ている祐一に、名雪がソファの後ろから声をかける。
反射的に振り返ろうとして、慌ててやめる。
どんな表情で彼女を見ればいいのか分からなかった。
何より、今名雪の顔を表面から見てしまうと感情を制御できる自信がなかった。
「…そ、そうか。大変なんだな…」
「………」
「………」
気まずい空気が流れる。
テレビの中では、今ちょうど「ナベの底の汚れをキレイに取る裏技」が紹介されていた。
名雪は、お構いなしに祐一とテレビの間に…すなわち、祐一の正面に回り込んで顔を覗き込む。
「…しないの?」
直球。
心臓が破裂するような音が聞こえた気がした。
「お…お、お前、何言って…」
いきなりの名雪の言葉に慌てまくる祐一。
無意識的に、視線が下がってしまう。
「勉強」
「だか………へ?」
「明日、数学の小テストだから、一緒に勉強しよって言ってたでしょ」
「……あ、ああ、そうだな、うん、しよう、うん」
違う意味で慌てて返事する。
(そういうことかよ…驚かせるなよ、まったく…)
安心すると同時に、今度は急に恥ずかしくなってきた。
一人で舞い上がって、一人で勘違いして…
(…まるっきりバカじゃないか…)
まともに顔をあげられないまま、とりあえず立ち上がる。
名雪も嬉しそうに…必要以上に嬉しそうに、その側にぴったりくっつく。
「えへへ…祐一、やっぱりえっちだ〜」
「…お前が紛らわしい言い方をするからだっ!!っつーかなんだ!?わざとだなっ!?その態度はわざとひっかけたなっ!?」
顔を掴んで容赦なくこめかみグリグリ攻撃を仕掛ける。
自分に対する恥ずかしさと怒りをそのままぶつけていた。
「うぅ…痛いよ〜…」
「自業自得だっ」
だいたい気が済んだところで手を離す。手のほうも痛くなっていた。
「ほら、とっとと行くぞ」
「…うんっ」
あっという間に復活した名雪が、またぴったりと寄り添う。
横から祐一の顔を覗き込むと、ぷい、と祐一のほうからすぐ目を逸らした。まだ顔が赤い。
それを確かめて名雪は密かに笑う。
「…なんだよっ」
祐一も気づいて、悔しそうに言葉を投げかける。
「だって祐一、まだドキドキしてるのが伝わってくるよ」
「…悪かったな、くそ…」
「悪くないよ。私も…ほら」
掴んでいた祐一の左手を自分の胸元に運ぶ。
「!?お、おいっ、何を―――」
慌てて振りほどこうとするが、体が凍りついたように動かなかった。
そして、否応なしに伝わってくる鼓動。
「ほら、ね…」
きゅ…と、名雪は両手でその腕を抱くように支える。
耳元にかかる息が、熱い…
「あのね、お母さん、9時まで帰って来ないんだって―――」
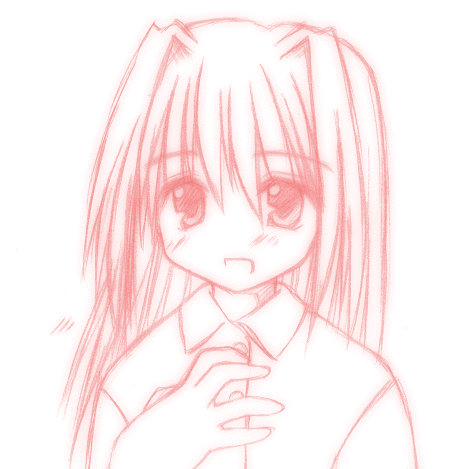
お・わ・り♪
【あとがき】
今回のラブラブ度:80%
ラブラブぱわー、ほぼ全開でございます☆
もう勝手にやってて下さいって感じです(笑)いやぁ…最近ラブラブ控えめだったし、先日「Body&Soul」っていうかなりマジメなもの書いた後だったからもうその反動でかなりハジけてみました。
栞に関しては…まあ、あんまり考えないようにしましょう(^^;
でもまだまだっ。まだまだこれでは目標である「読んでる途中に恥ずかしくて身悶えてしまうよーな」SSというには程遠いですっ!目指せ100%☆