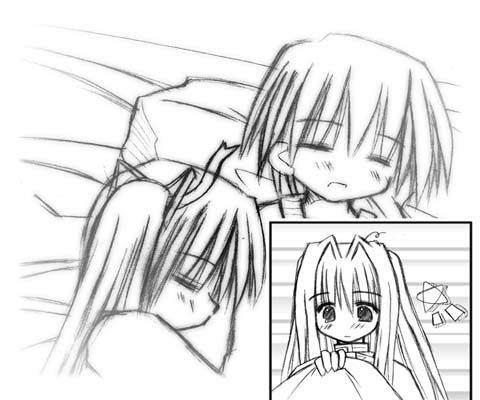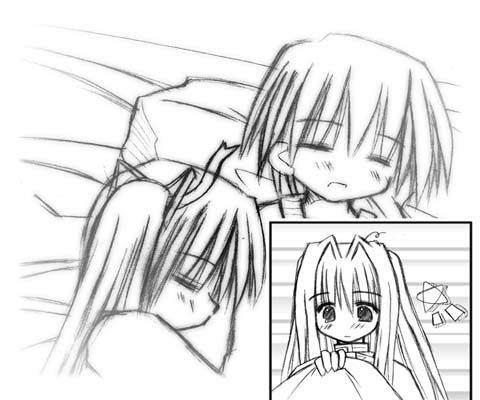その日は偶然早くに目が覚めた。
まれに、そんな事もある。珍しいが、異常な事でもない。
ただそれだけの普通の朝だった。
「………7時…」
名雪は目覚し時計…のうちの一つ…の表示で時間を確かめる。
四角いシンプルなものから可愛らしい猫のデザインのもの、デジタル表示のものからアナログ表示のもの、数字の表示もアラビア数字だったりローマ数字だったり書いてなかったり。多種多様なまるで目覚し時計博物館のような景観の中、一つ特にお気に入りのものを手に取って目の前に持ってきて改めて時間を確認する。
確かに、針は7時を示していた。
すう………っと大きく息を吸って目を閉じる。
今日の授業は何だっただろう。水曜日……そうだ、午後に体育がある。体操服を忘れないようにしないと。
数学の当てられてる問題はちゃんとやったし…うん、大丈夫。…出来のほうは大丈夫じゃないかもしれないけど。
そうだ、今日は陸上部の練習もないんだっけ。グラウンド…何に使うって言ってたか。
ってことは祐一と一緒に帰ることができるんだ。ちょっと嬉しい。
…色々な思考が頭の中をぐるぐると駆け巡る。
そして、ゆっくりと目を開く。眩しい光が目に入ってくる。
「…7時1分」
当たり前だった。
「うにゅう………」
二度寝するほどの時間は無い。起きなければいけない。
布団の中でもぞもぞを体を動かして、起きるための準備をする。というより、体を動かして布団の暖かさを体に十分に味あわせる。最後の悪あがきだ。
布団の外は別世界。一言で言えば、ひたすら寒い。
体温で暖かくなった布団の中は、まさに一番気持ちいい温度に保たれている。布団から出られないように何かの力で仕向けられているようだ…なんて考えてみる。
「起きるよー」
とりあえず言葉で気合を示してみる。
「…くー」
空回りする。
やっぱり名雪は名雪だった。
一瞬布団の中に入り込んだ冷たい空気に耐え切れずまた閉じこもってしまう。
「うー…せっかく起きたのに………また祐一に起こされる…」
それもいいんだけど、と甘い誘惑に駆られてみたりする。そうすればもっと寝ていられるし、今日も祐一が部屋に来てくれる。…だけど、ちょっとだけ悔しいのも事実だ。
祐一は…祐一はもう起きただろうか?
いつも何時くらいに起きているのだろう。
祐一の顔が脳裏に浮かぶ。いつも文句を言いながら優しく―――優しくはないかもしれないけどでもいつもちゃんと起こしてくれる。迷惑がってはいない…と思う。
でもできるだけ一人で起きたほうがいいに決まっている。それは分かっている。
それに…
「たまには…わたしのほうが起こしてあげる………」
考えるより先に言葉のほうが出ていた。
言ってから考える。
(わたしが…祐一を…起こす)
素晴らしい名案だと思った。きっと祐一はすごく驚くだろう。驚いて―――
「おはよう、祐一」
「……名雪…?」
「わたしの方が起こしてもらってばかりじゃ不公平だからね、頑張って起きてみたんだよ。祐一を起こそうと思って…」
「名雪…俺のために、そんな無理をして―――」
「だって…祐一が喜ぶと思ったから。祐一が喜んでくれると思ったからわたし頑張れたんだよ」
「…ああ。嬉しいよ。すごく…ありがとな」
「うん。さ、起きよ?」
「なあ―――王子様は姫様の口付けで目覚めるんだぜ?」
「もう…勝手なんだから………」
祐一は優しく微笑んで目を閉じる。
わたしはゆっくりと顔を合わせて、近づけていく―――
………と。
(きゃっ…祐一ったらそんな強引にっ)
(あ、ちょっとぉ…キスだけじゃなかったの〜?)
(もう…仕方ないなぁ……今日だけだよ?)
(あ…っ、ダメだったら…これ以上はお母さんに気付かれちゃう…真琴だっているんだから…)
(う、うん…もうっ、祐一のエッチ………)
………………
「………はっ!?妄想爆裂してる場合じゃなくてっ」
手に持ったままの―――強く握っていたから手が痛い―――目覚し時計の表示を改めて見てみる。
「7時12分」
がばっ!!
勢いよく布団を跳ね除けて起き上がる。体は十分にホットに出来上がっていた。
「待っててね、祐一っ!今日は記念日になるんだからっ」
何の記念日だ。
そして出口のドアを元気に開け放つ。
「さて…」
ここは祐一の部屋の前。「あいざわ ゆういち ここにねむる」というプレートがドアの前に掛けられている。どうやらまだ寝ているらしい。
(真琴のプレゼントを素直に使っているのがちょっと悔しいんだけどね…)
このプレートは、真琴が殊勝にも「いつも世話になっているお礼」ということで家族全員に手作りのプレゼントを渡した時のものだ。その時祐一は「俺の墓を勝手に作るなっ!」とか言って怒っていたものだが、なんだかんだ言って使っているところを見ると悪い気はしていないらしい。
それが名雪はちょっと悔しい。
ちなみに名雪へのプレゼントは紙工作で作ったネコ型貯金箱だった。全然まともに使えない出来だったので使っていない。というか明らかに祐一のものと比べて気合いの入れ方の差を感じたので次の日ちょっといじめてやった。
靴に小石を仕込んでおいたり。
…まあ、それはさておき。
1.「おっはよーっ!」元気よくドアを開ける。
2.とりあえずノックして確認する。
3.こっそりと静かに開ける。
というわけで躊躇無く、音を立てないように静かにドアを開けた。
部屋の中はまだ暗い。起きていないのは確実のようだった。
起こす目的で来たのだから別に静かに歩く必要は全くないのだが、名雪は細心の注意を払ってベッドに近づいていく。明かりも点けない。
ベッドにたどり着くと、布団を少しだけずらして祐一の顔が見えるようにする。
「わあ…祐一の寝顔、初めて見たよ……」
ちょっと感激してみる。
もともと可愛い系顔の祐一なだけに、寝顔はなかなか素敵なものだった。…少し、あまり見てはいけないものを見たような気がして恥ずかしくなる。
(祐一も、わたしの寝顔見ていつもこんな感じしてるのかな…)
慣れていると平気なのかな、と同時に自分に問いかけてみる。
ドキドキしながらも、せっかくだからと改めて観察する。
茶色がかった綺麗な髪。
今は閉じられている、少し意地の悪そうな目。
北国の人間にはあまり見られない、ほんの少し褐色がかった濃い目の肌。
中性的な印象は否めないが、やはり世間的にもいい顔だと言っていいと思う。
(本当の魅力を知っているのはわたしだけなんだけどね♪)
と、心の中で一言付け加えておいて。
例えばこのパジャマ姿。これだけでも見たことのある人間など数えるほどしかいないだろう。
名雪は他の誰も知らないような祐一の姿をたくさん知っていると自負している。その点で既にライバル多数と大きく差をつけている自信がある。
そう例えばこの布団から姿を覗かせる真っ赤なリボン―――
………………………………
………………
………
名雪は数秒間、色んな事を考える。
どう見ても女の子のリボンだ。そりゃ一回か二回か三回くらい祐一に「女の子のカッコしても似合うんじゃない?」って言ってみたりしたけどこのリボンはどうなんだろう。だいたい寝ている時にしてても誰も見ないから意味ないじゃない。ちゃんとわたしに見せてくれないと。
それにこれ頭につけるものだよね。どう考えても服のどこかに付けてる感じなんだけど見なきゃわからないけどねそうだ見てみよう。
そっと、もう少しだけ布団をめくってみる。
オレンジ色の髪の毛が姿を現した。
「………………」
ここ3ヶ月で最高記録というくらいの思い切りの力で布団をがばっと引き剥がす。
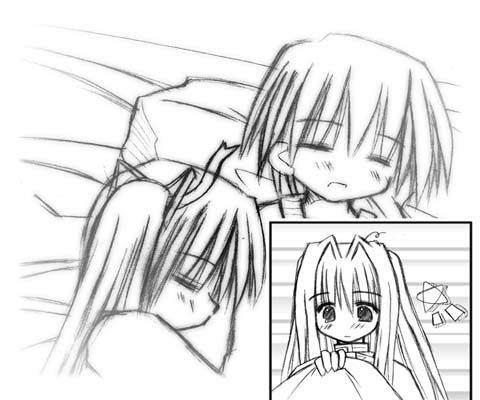
「……寒い…」
「………あう」
祐一が寝ている。
その隣に寄り添うように真琴が寝ていた。
名雪は思考が回りはじめるより先に右足を思い切り振りかぶって真琴の尻を踏みつけていた。
そして、考える。
なんで真琴は寝るときも髪を解かないのだろう。
………
…そうじゃなくて。
「どうして真琴が祐一のベッドで寝ているのかな?」
可愛らしく首を傾げながら独り言を言ってみる。
その右足は思い切り真琴を踏みつけたまま。
「不思議だな…」
そのまま足で蹴る。蹴る。蹴る。
「うぅ…ん………」
真琴が唸りながら転がって無意識的にそれをかわそうとする。結果、祐一のほうにさらに近づく。
顔は祐一の首元に、手は胸の上に、脚は祐一の脚と交差するように…
「な、な………何どさくさに紛れてわたしの祐一に手を出そうとしてるのっ!?このヘンタイっ!泥棒っ!!いざという時の水瀬家共通非常食っ!!」
怒っていてもお約束どおり3つ目にボケる事は忘れないあたり、名雪は偉かった。
…何が。
「うー…何よぉ…朝からうるさいわねー……」
真琴が少しだけ目を開ける。
目が合う。
「ほら答えなさいよっ!!なんであんた祐一のベッドに潜り込んでいるのっ!?」
「そんなの一緒に寝たからに決まってるじゃない……足、どけてよ。勝手に踏まないで」
むか。
「何よ真琴のクセに一端の人間様みたいな口聞いて!?一緒に寝たって!?ふざけないでっ、どうせ無理矢理潜り込んだくせにっ!このままわたし右足に体重かけたら凄いことになるんだよそこんとこ分かってる―――」
「…なんだよ………何騒いでんだ……」
「あ、おはよ〜、祐一♪」
真琴に続いて今度は祐一が目を覚ます。
そりゃまあベッドでこれだけ騒いでいれば。名雪でもない限り誰でも目を覚ます。
祐一の目がうっすらと開くと同時に名雪は足をさっとベッドの上から下ろす。
そしてさも何事も無かったかのようににっこりと微笑みかける。
ただし今度は祐一の死角になる場所で、右手で真琴の太ももを思い切りつねっている。
「………っだーーーーーーーーーっ!!!!!何すんのよこのアホっ!!それあんた自分が思ってるよりはるかに痛いわよっ!!?」
なるほどそれはいい事を聞いた、と心の中で名雪はニヤリと笑いながら、
「んん?どうしたのかな真琴。蜂にでも刺されたのかな?」
天使のスマイルを浮かべながら事無げに言ってのける。
祐一は目を覚ますなり目の前で繰り広げられる謎の騒動に巻き込まれて、正常に思考が働かない。
(…整理してみよう)
「ム…ムカつくわねっ!!ちょっと祐一っ、この凶暴女をなんとかしてよっ!!ちゃんとしつけてくれないと困るわよっ」
(…真琴がなんか怒っているらしい)
「な、なん………い、いやいや。ほら真琴、そこにいたら祐一が起きるのに邪魔でしょ?ちゃんとどいてあげないと」
(…名雪が………随分抑えているみたいだがどう見ても内心キレてるのがはっきりと分かる…)
はた、と。気付く。
真琴はベッドの上にいる。というか寝ている。祐一の隣に。
名雪が祐一の部屋にいる。ベッドの側にいる。
…目を閉じる。
(つまり…俺と真琴が一緒に寝ているところを見つかったわけだ………)
一瞬体全体に凍りつくような寒気を感じた。
ようやく今の状況の危険さを思い知る。
「ねえ、祐一からも言ってやってよ。このアホ女、真琴が勝手に祐一のベッドに入り込んだなんて思い込もうとしてるのよっ。ちゃんと言ってあげなさいよ、確かに一緒に寝ました、それ以上の事もありましたって!」
そして祐一は頭を抱える。
破滅の音を聞いた気がした。
「………なんて?祐一―――ホントなの?」
名雪は視線で信じてるよ祐一の事、と訴えかけながらじっと見つめて言う。
眩しかった。
と、同時に真横からも祐一を見つめる視線。
何とも読み取れない表情の真琴と目が合う。
(それ以上の事―――ああ……間違いなく、あったよ………間違いなく)
昨夜の事を克明に思い出す。そう…一緒に寝ただとか、そういう次元の事ではない。確かに「それ以上の事」はあった―――
思い出したくもない。
でも、カラダに残った感覚がそれを忘れさせない。
本当はどこかにそれを喜んでいる自分がいるような気がする…
だけど。
(言えるわけがない………)
「あー…一緒に寝たのは、確かだ。真琴が寂しがってな………」
とりあえず思いついた言葉を言ってみる。信憑性なんて考えている余裕もない。
名雪は不満そうに顔をしかめる。
「真琴が寂しいっていったら一緒に寝るの?何よそれ…幼稚園児じゃあるまいし。あ、そうか、真琴は似たようなモンかもね。まだ一人じゃ寝られないんだ。ふーん」
………
祐一はこの時名雪を世界で19番目くらいに怖いと思った。
しかし真琴はこの挑発にも余裕の笑みを浮かべて名雪を見返す。
「やれやれ…真琴が幼稚園児っていうんなら名雪は新生児ね。まだ分からないの?真琴は、祐一とえっちしたって言ってるの」
そして真琴は世界で12番目くらいに怖いと思った―――
「………………祐一…本当に?」
すでに目が濁っている名雪。
祐一に、黙りとおす勇気は無かった。
「あ…ああ………したというか、されたというか………」
「ほら見なさいよ♪わかったなら邪魔者はさっさと出てってよねっ」
言葉を濁す祐一に対して、完全に勝ち誇ってむしろ楽しそうな真琴。
名雪は―――
「…そう」
俯いて低い声で一言だけ。
呟くと、よろよろと危なっかしい足取りで歩き、静かに部屋を出て行った…
ぱたん。
部屋のドアがゆっくりと閉じられる。
「………」
”大荒れ”を覚悟していた祐一は、そのあまりに意外な反応にしばらく呆ける。
真琴は真琴で、いつでも闘える準備をしていたのにあっさりと相手が引いていって拍子抜けして固まっている。
「な…泣いちゃってるのかなっ」
「分からんが…なんかヤバげな感じはしないか?」
「ま、真琴は悪くないからねっ。最初にいじめてきたのは名雪のほうなんだからっ」
…そうだったのか、と祐一は少し納得する。真琴の態度も必要以上にキツいなと感じていた。
まあ、元からあんまり仲良くは無さそうだとも思っていたが。
「…とりあえず、起きるか」
食卓に着いてみれば、もう普通の名雪だった。
「いっちごジャムジャム〜♪パンいっこにスプーン5杯〜♪」
「………」
「………」
祐一と真琴は席につきながらそんな様子をじっと眺めてみる。
「ん?どしたの祐一、食べないの?」
「あ…いや、食うぞ。おお。もうリミット一杯までいける覚悟だ」
いつもの幸せそうな顔で声をかけられた祐一はちょっと慌ててパンに手を伸ばす。
「…ね、ねえ、名雪?」
「祐一、ジャムは欲しい?たまにはどう?いちごジャム、おいしいよ」
「いや、いい…」
祐一は隣の真琴をちらっと見る。
見事にスカされた真琴は手を少し前に出した状態で止まっていた。
もう一度、慎重に口を開く。
「あの…今朝のことなんだけど…」
「今日もあんまり時間無いから急いで食べないといけないねっ。頑張ろうね祐一♪」
「………」
差し出している手が震える。
ちょっとヤバい、と祐一は経験から察知する。今ここで真琴が爆発するのは好ましくない。
間違いなく祐一に一番とばっちりが来る。
「なあ、名雪」
「うん?」
「まこ―――」
「あ、ほら、時間だよっ。しゃべっている暇なんてないんだから。急ぐよっ」
「………ああ」
完全に存在そのものを無視する作戦のようだ。真琴の名前を出そうとするだけで遮られてしまう。
その反応に真琴はしばらくふるふると体を震わせていたが、やがてすっと力が抜けたように手を下ろし、視線を下げる。
不思議そうに祐一がその様子を見ていると、真琴はにこりと笑って見せた。
それで、安心する。
「さ、一緒に学校行こっ。二人で♪」
わざわざ二人で、と強調して、名雪が立ち上がる。実際結構厳しい時間になっていた。
祐一も立ち上がって着いていく。
「んじゃ、行ってくるぞ」
真琴は笑顔でひらひら〜と手を振って答える。
そして、二人とも部屋を出て行った。
「…ふん」
真琴はそれを確認すると、ドアに向かって冷たい視線を送る。
「せいぜい頑張ればいいわよ。どのみち祐一は真琴のモノなんだから…」
長い一日が始まった。